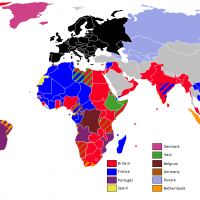⭕️皇帝から中国共産党を貫く支配正統性の証となる大一統,天下思想,儒家正統の解明!
辛亥革命以前に中華天下すなわち現在の中国エリアを支配してきた諸王朝が、その支配の正統性を調達し、その存立基盤として必要不可欠となっていた根拠を構成する要素について検討していく過程で、中華天下を「帝国」として支配するための根拠となる主たる構成要素として浮かび上がってくる「大一統」「天下思想」「儒家正統」などの原理的な概念について検討していきます。
「帝国としての中国」の基本類型としての「多重型」帝国と「多元型」帝国の検討
歴史上における「中華帝国」は、その支配者の出自も踏まえて基本的に「多重型」と「多元型」の二つの類型に分類できると言えよう。
前者は発祥地が「漢人地域=中華」であり、主として「一元的天下」「三重的構造」「周辺の四夷」と言う三つの要素を備える帝国構造を指し、後者は「周辺の四夷」エリアにおいて成立し、その後に中国に入る征服王朝で正統な中華王朝を志向しながらも純粋な民族的性格や民族の根拠地を重視する帝国構造を指す。(1)
この類型に従えば、例えば隋唐、宋、明などは前者となり、遼、金、元、清などは後者となろう。考えてみれば中華世界を、漢族が完全に支配していた時期と言うのは、そんなに長いものでは無いとも言えそうである。10世紀からの1000年間でも宋は、北部地域を遼や金に支配されており、挙句の果てが元による中華世界全面支配に至った。その後、ようやく明が中華世界を全面的に漢族の天下を回復するが、それも1368年から1644年までの間だけで、その後は中華世界全体が清の全面的な支配を受けた。そのように考えると中華世界においては、総じて多元型の中華帝国が優勢だったと言えようか。
漢人支配者による「多重型」中華帝国の構造
漢人支配者によるいわゆる「多重型」の中華帝国構造においては、「中華」と「四夷」の関係は流動的であり、「中華」を第一地帯とすれば「四夷」は第二地帯、あるいは第三地帯となる。第二地帯と第三地帯の相違は、第二地帯は中華に接しており中華帝国の主権の範囲内であるが、第三地帯は「属国」として中華帝国が「宗主権」を持つエリアとなる。第一地帯は第二地帯が中華文明に漢化され変質することで拡大し、第二地帯も第三地帯の変質により拡大するという流動性を持つ。このように漢人支配者による中華帝国においては中華文明圏の拡大が、直接統治領域や主権領域の拡大につながっていく。(2)
このような多重型中華帝国構造における中華文明圏の拡大現象であるが、これにははっきりとした限界があったと言わざるを得ないだろう。すなわち、この領域は明の最大版図を限界として内陸部への拡大は困難であったと思われる。これは漢民族の居住領域とほぼ同一エリアであり、清朝においてはっきりした中国内地と藩部の領域・境界における中国内地エリアが、中華文明圏の限界だったと言えようか。
異民族支配者による「多元型」中華帝国の構造
異民族支配者によるいわゆる「多元型」の中華帝国構造においては、帝国の主権領域が「中華」と「支配民族エリア」という二つの地域からなるが、帝国の主権・宗主権を持つ「支配民族」が「中華」を包囲する形で「四夷」を形成する格好となる。この場合にも「中華」の漢人の「中華意識」は消えることがなく、「異民族支配者」側も「中華」文明をそのまま優越的存在として受け入れることは無い。基本的に「多元型」中華帝国においては「異民族支配者」は人口的には圧倒的に少数の集団であり、元における「モンゴル・色目・漢人・南人」、あるいは清における「満・蒙・旗・漢」と言うような民族的身分制度を採用し「異民族支配者」以外の他民族の力も借りて「中華」支配を実施した。「多元型」中華帝国においては、このような支配構造を継続する中で帝国における「中華」の重要性の再認識や政治的重心の中華への移行が不断に継続され、異民族支配者そのものの性格が徐々に「中華」化していくような傾向が底流に常に存在した。(3)
このような多元型中華帝国においては、その領域は中華文明圏を超えた広がりを観せることが多く、特に清においては乾隆帝時代に最大版図を形成するに至った。多元型中華帝国においては、中国内地と異民族領域の統治をどのように両立させるかが課題であり、この状況は帝国的構造を内包する現代の中華人民共和国にも引き継がれてきていると言えよう。
中華世界に成立した「中華王朝」の帝国性の検討
ここで中国に成立した「中華王朝」の帝国性について再検討してみたい。
「中華王朝」の基本的性格
中華王朝については、「中華世界」の地域全体か、その一部を支配して都城を築き中央集権的に皇帝が支配する政治体制の下で、「儒家正統と漢字文化」を基調に統治する王朝であり、いわゆる「中原」を「中華文明」に基づき支配する「王朝国家」と言えよう。(4)
このような中華王朝国家は歴史上に数多く存在した。五胡十六国の各国も五代十国の各国も、このような条件に当てはまる国家であったと言えよう。しかし、本ブログのテーマである「中華帝国」としての有りよう備えるかどうかとなると条件が異なってくる。単なる「王朝国家」と「帝国」としての実体を兼ね備えた国家とは別次元の存在であった。すなわち「中華王朝」が全て「帝国」としての実体を備えていたかと
いうと、そうとは言い切れない。
「帝国としての中国」成立のための条件
「中華」あるいは「中国」として自らを認識出来るためには、中央の「中華」と周辺の「非中華=四夷」が「王朝国家の内部」に存在することが必要であり、そのような「四夷」をも取り込む「大一統」を実現した国家のみが「帝国」としての実体を備えていたのであり、「中華文明=漢人エリア」だけでなく「四夷=非漢人エリア」も天子の威令で従わせることが「大一統=中華帝国」成立の要件であった。(5)
このように本ブログ全体の主題でもある「中華帝国」成立の基準は、王朝が「中華」だけでなく周辺「四夷」を支配下や勢力範囲に取り入れているかどうかということであり、周辺の「四夷」を支配下や勢力範囲に取り入れた「大一統の状態にあること」こそが「帝国としての中国」の本質である。これは現代の中華人民共和国にもそのまま引き継がれており、沿海部から中原地域を中心とする漢族地域のみならずチベット、モンゴル、新疆エリアを完璧に掌握してこその「大一統」であり、「大一統」の成立の可否は支配正統性にも直結する最重要課題となるだろう。
こうしてみると、外モンゴルを喪失した蒋介石率いる中華民国が中華世界の支配正当性を「喪失」し、中華世界から退場することになったことも説明出来るかもしれない。
中国支配の正統性根拠
基本的に歴代の中華王朝は、「大一統=中華帝国」を目指し、かつ人々からもそのように期待される存在であったが、一方で「偏安」(一地方に割拠して統治)に甘んじる王朝は、「大一統」に反する無能な王朝として非難されるだけでなく、政権や支配層の正統性が追及されることとなった。例えば三国時代の呉は中華王朝としての正統性が問われており、「偏安」の典型である「南宋」はモンゴルに滅ぼされ中華を失うことで皇帝の天子としての「正統性」が問題視されている。(6)
このようなわけで、史上の中華王朝は「正統」性を証明するために「大一統」を志向し、「中華帝国」の実体を追い求めてきたと言えよう。およそ「中華世界」において政権を確固として維持していくためには、「王朝」として成立しているだけではダメで、「中華帝国」としての実体を有している必要があったわけであり、それには「大一統」が必須要件だったということである。
このあたりの状況は、「中華世界は広すぎて統一はなかなか困難であるので適正な領域に分割して支配すべき」と言う一見効率的な統治体制かと思われた三国時代の「天下三分の計」が、その後二度と再び顧みられることがなかったことからも窺い知れよう。
中国支配の正統性必須要件としての「大一統」
「中華における支配の正統性」は、支配者の民族的出自で判定されるのではなく、「大一統」を実現することができれば、それは正統の「中華王朝」の要件を満たすと考えられた。このような正統性の問題を突き詰めて行くとそこには「中華」的な政治上の神話が浮かび上がってくる。すなわち「正統」の根源は「天」で、「天が一つ、天下が一つ、天子も一人」であり、天下のあらゆる民は、天が選んだ天の代弁者である天子に従うべきだ、と言う考え方である。(7)
中華帝国統治のための基本的イデオロギー
董仲舒による中華統治のイデオロギーの体系化
漢の儒者の董仲舒は、「儒家正統」の「儒教」化、神学化に貢献したが、その中で彼は「天人合一論」「天人感応論」を打ち出し、儒学の諸学から離れた「独尊」的な立場を確固たるものとした。また董仲舒は、「天子は天から受命し、天下は天子から受命する」「天地・陰陽・四時・日月・星辰・山川・人倫を通じ、徳が天と地に達す者は、皇帝と称す。天は其れを子息と見做して守り、天子とたたえる」との見解を披歴し、「天人三策」において、「一統は、天地の常、古今の道」と述べて、漢の武帝に「中華帝国」の理念として提言した。
このように「儒家正統」は、董仲舒により、「中華帝国」の存立に不可欠な理論的基盤を提供し、周代から継続してきた「天下思想」が、中華帝国の統治イデオロギーとして体系化された。(8)
こうして、董仲舒によって「大一統」「儒家正統」「天下思想」が一体化し、「中華帝国」の統治イデオロギーとして理論化、体系化され、清朝崩壊まで一貫して継続されてきたと言えよう。現代の中華人民共和国においても「儒家正統」の指導イデオロギーの地位はマルクス主義や毛沢東思想等に変化してきてはいるもののベースとなる「大一統」の方向性や「天下思想」の在り方が、大きな変化を受けていないのではなかろうか。
「天下思想」における「政治秩序」の論理
「天」を最高権威とする「天下思想」において政治の秩序は、「天」「天下」「天子」「民」の四者の関係で構成されるもので、その関係 性は「支配者が天から天命をうけて天子になり、天子が「徳冶を実施して民が服従し、「華」と「夷」が服従して「大一統」としての天下が成立する」というものであり、循環的に「天下」が成立することで天の意志が実現される」とされた。このような四者の関係において、「天下」の最高権威は「天」であり、地上の支配者である皇帝は「天」から「天命」をうけてはじめて「天子」としてみとめられるのであり、「天」は民とは直接関係せず「天命」を与えた「天子」あるいはその治める「天下」を仲介とするとされた。すなわち地上の支配者たる皇帝も「天子」として「天」の意志に従って行動することが求められ、「天命」を見失えばその地位が失墜するような存在であった。そういう意味では、この四者の関係は、「天命」と「天子」の支配の正統性を巡って緊張感を孕んだ微妙なものであったともいえよう。(9)
「天下思想」と「民意」の反映としての農民大反乱の正当化
この論理については、単なる机上の空論とは言えないであろう。清朝以前のあらゆる王朝は大規模な農民反乱を鎮圧しきれずに崩壊しているのであり、これは日本のような「万世一系」というかなり特殊な国体を維持してきた状況から見れば変化に富み、民意を反映するシステムであったと言えるかもしれない。このような支配の正統性を巡る構造は、現代の民主主義とは異なり、選挙の時期や議員の任期が決められたものとは言えないが、民意の最低限の保証を担保し、暴虐で非人間的な政治を牽制するような役割を果たしていたのではないかと推測される。人民は本当に耐えがたくなれば、少なくとも300年以内にあらゆる王朝を倒すだけの力は確保していたと言えるのであろう。
「天下」の範囲と「大一統」の実現
このような「天下思想」の在り方を俯瞰すると、「天命」をうけた「天子」の徳冶の対象は、中華の民に限られるのではなく「四夷」の民も当然ながら徳冶の対象として予定されているのであり、「中華帝国」の有りようとしては、「大一統」により「四夷」も取り込むべく領域拡大に精励することが「天子」の本分として期待されていたとも解釈できよう。またそのような「大一統」を実現し維持しているという、そのこと自体が、「徳冶」の証左であり、「天子」たる皇帝が「天命」をうけて天に支持された正統な存在であることを天下に明らかにする絶好の機会でもあった。
このようなわけで、歴代の中華王朝は、その「大一統」の「中華帝国」的性格が色濃く強力な支配体制を確立しているほど安定していると言えるのであり、本論文でも取り扱う「清の極盛期」はそういう意味でも典型的な時代と認識している。
「天下思想」と「天命」による支配正統性の調達原理
このような「天」「天子」「天下」「民」と言う四者関係において、「民の側が天命をうけた正統な天子に支配されることに納得し、民の側から聖天子と称え得るような状態」が現出していれば支配の正統性は何重にも担保されることになるであろう。「天下思想」は歴代中華王朝にそのような機会を提供し、「大一統」の天下を上手く「演出」あるいは「実現」できた王朝にはその実力の何倍もの恩恵をもたらすとともに、天命を失った王朝の存在を否定し歴史から退場させる論理を供給し続けて来たとも言えよう。
2020年の天変地異が中国共産党の支配正統性に与える影響
2020年段階においては、主として毛沢東思想をその支配の基礎に置く習近平が、帝国統治者として君臨しているわけであるが、2020年初頭に勃発した武漢を中心にした所謂「コロナ危機」は辛うじて乗り越えたものの、2020年5月から6月にかけて西側民主主義列強の反発を無視して香港への国家安全維持法制の導入を強行したあたりから、あたかも天の怒りを買ったかのように長江領域における例年にない豪雨と洪水被害が発生しており、遂には三峡ダムが限界に陥り長江の水利調節の役割を果たせていない、との報道もなされる事態となっている。
中国には、西側民主主義国のような選挙による民意の政治への反映は無いわけであるが、これ程わかり易い観測史上に残るような水害の発生についての天意を中国共産党はどのように説明して、その支配正統性を天下に明らかにしていくのかは、関心を持って見守るべきであろう。
このあたりの状況は、現代における中国共産党が中華天下を統治する資格に直結しており、香港問題や台湾問題を遥かに凌ぐような、天意と天命、支配正統性を巡る天下の趨勢に関する新たなる重大な緊張関係を孕んでいるのではなかろうか。
私見では、このような事態の延長線上には、秦の始皇帝による中華天下大一統、孫文による辛亥革命、毛沢東と中国共産党による中華併呑に匹敵する激動を惹起する可能性もありうると思量せざるを得ないところである。
少なくとも易姓革命の論理と歴史的な展開からすれば、王朝を崩壊させる規模の農民大反乱が近いうちに発生しても、満更驚くべきことでも無いような気がする今日この頃である。
尚、中華王朝の交替をめぐる宿命論的な循環については次項の課題とする。
現代に通じる魏晋南北朝期の中国の混乱要因と北魏による中華大一統再現策の効果の分析!
トランプ大統領の不法移民流入制限の根拠は魏晋南北朝時代の中国の混乱が証明する!
継続課題
「天・天下」と「帝国」の関係性の論究。「統治の正統性」の根拠の検討。
参考文献
(1)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p200
(2)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p201
(3)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p202
(4)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p203
(5)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p203-p204
(6)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p205
(7)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p206
(8)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p207
(9)王柯:帝国の研究 名古屋大学出版会 2003 第5章 「帝国」と「民族」 p207-p208